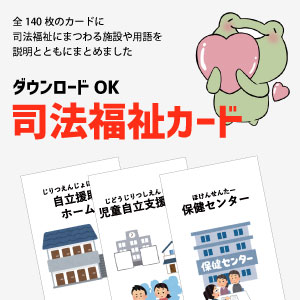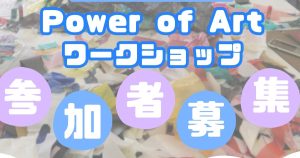《街のよりそいさん数珠繋ぎ》(インタビュー11回目)
〈インタビュアー〉:廣田貴也
〈インタビュー日〉:2023年8月24日(木)
〈今回のよりそいさん〉:石野英司さん
10数年ほど前に就労支援業務として南大阪自立支援センターを設立。
父親である先代がクリーニング関係の業務を主体とする株式会社にて障がいがある方の雇用を実施されており、物心がついたときより、障がいのある方との関わりをもっていた。
車をご趣味とされており、休日はお孫さんと一緒にドライブ、奥様と温泉に行くなどして過ごされている。
Q.普段、どのようなお仕事をされているのでしょうか。
石野さん:まずクリーニング関係の業務をしており、そこで障がいをお持ちの方が多数働いております。また刑余者の方も多いのでその方々の就労支援、障がいをお持ちの方のサポートも行っています。具体的には訪問看護事業と障がいのある方向けの計画相談事業を実施しており、さらに近年はグループホーム事業も開始し、現在3棟運営しております。
グループホーム事業では、罪を犯した方の帰住調整等で地域生活定着支援センターからもお話をいただくこともあり、お話の中で弊社の方で働きたい、暮らしたいという方を受け入れています。昨今罪を犯したということでお断りされる方も多く、それならば弊社でグループホームを起業して受けいれることが出来ればという思いから、グループホームを5年程前に企業しました。
Q.どのような思いから今のお仕事に就かれたのでしょうか。
石野さん:元々先代がしていた仕事で、障がいをお持ちの方と関わっていました。今では就労支援があったりしますが、半世紀前では障がいをお持ちの方は社会参加がしにくい時代でした。どちらかというと自宅の中で親御さんが世話をされていることが多かったと思います。ただ私自身の関りの中では、そのようなことが全くなくて、階段をスムーズに上がれない、自分でトイレに行くことも難しいといった今でいう福祉サービスの生活介護に来られる方であっても、持ち場を複数人で協力しながら働いていました。ただ、雇用している中で、帰りに万引きしたとか、事件・事故を犯したなどで警察に保護されているということがありました。その際、中々親御さんが来てくれないということがあり、親御さんの代わりに代理人という形で身元を引受け、一緒に頭を下げて連れて帰ることなど行っておりました。そんなこともあり特に抵抗もなく法に触れた人へ「寄り添う」、「一緒に社会参加できるようなお手伝いをする」という経緯で始めて、今に至ります。
また私自身も身体障がい者で1級の手帳を持っており、学生時代は激しい運動をすると倒れ搬送されることも度々あり、就活でも履歴書に記載すると書類選考で不採用になることもしばしありました。それでも上手く面接を通過して身体の事を正直に話すと不採用になるなどしんどい思いをしたこともあり、自分の中でも障がいを持っている人が社会参加するのは容易くないという思いがあったのが今につながっていると思います。
Q.これまでお話いただいたことのほかに司法福祉に関わることはございますか。
石野さん:これまで十数年ほど協力雇用主を行っています。その縁で保護観察所での合同面接会に出席したり、また新しく協力雇用主さんになった方々に協力雇用主としての心構えや遣り甲斐などを講話する機会を頂いたりしています。また少年院や保護観察所、就労支援機構などを通じて雇用したりもしています。また再犯防止室からの相談や問い合わせなどケースワークにも対応しております。
Q.お仕事をされている中で大切にされていることは何ですか。
石野さん:罪を犯した方、障がいをお持ちの方、健常者の方含めて言えることなんですが、人を表面だけで人を判断してはいけないということは常々言っています。私たちは支援者ですが、支援者=偉いではないと。サポートしたり、助言したり、時には叱ったり指導していくこともあるが決して偉くはないとよく言います。当事者である利用者さんと同じ目線で接して、特性を理解し、かみ砕いてポイントを示していく様に意識を持って関わることが「寄り添う」という意味でもっとも大切だと思っています。丁寧にアセスメントを行いその人らしさを理解して関わることができるように励んでいければと考えております。
Q.自立支援とはどのようなものだと考えておられますか。
石野さん:本人のエンパワメントやストレングスを高めていってあげて、本当に文字通りに「自立」できるようにすることが概念かなと思っています。様々なハンディキャップを持っている方がいるので、その人の強みをより生かしてあげ、援助していくということです。将来的には一人暮らしを目指すことが前提とはなりますが、本人の思いを大切にしてあげて、援助する側がその人の力を引き出してあげて、強制するのではなくて引き延ばしてあげるというのが私の考えとしての自立支援ではないかと思っています。
Q.支援を更に充実させるために欲しい制度や現状の課題等はございますか。
石野さん:制度設計において骨組みがあっても、判断が自治体任せになっていることが課題だったりします。福祉サービスや支給決定、区分にしても、法律がしっかりしていても自治体の解釈がちがいます。県によって、支給を受けるために必要な証明書や意見書の提示の簡素化であったり、また入口支援として支援が必要な方に関わることもありますが、今の制度では出口支援が基準で、入口支援では加算対象にならないなどと課題があります。
国としての罪を犯した方に対する支援、社会参加の機会を設けていきましょうという思いは素晴らしい事ですが、しかしながら現状の制度では支援する側の立場と温度差があります。制度の認識は自治体(窓口判断)で判断されるので同等のケースでもこの市は支給決定されたけど別の市では支給決定されないということが多々耳にすることがあります。統一されていないことで困惑するのはいつも事業者なので国も明確な判断基準を設けて欲しいと訴えていこうと思います。
Q. 今後の目標などはございますか。
石野さん:ソーシャルファームをもっと広めたいと思っています。生きづらさを抱えている人達にとって暮らしやすい社会の実現と孤立を引き起こさない為に出来ることを含めそういった立場の人達の居場所創りや雇用を創出していく意味でもソーシャルファームはとても重要だと痛感しております。
Q.市民の方々にお伝えしたいことはございますか?
石野さん:罪を犯した障がい者の方の話を聞くと、真っ先に罪名に目がいくことでしょうね、「皆さん怖い」と思われるかもしれませんが、決して罪名だけで判断しないでほしいと思います。犯罪に手をそめるまでには様々な背景があり、必ずしも犯罪をしようと思ってしている人は少なくて、お腹がすいていたとか、相談する人がいないなど孤立している経緯が多くあります。事前に相談する所や人がいれば法に触れることを防ぐことができたのではないか?と考えさせられることが多々あります。問題はそのような社会になってしまっていることが残念であります。社会責任として官民一体で考えていけば、きっと明るい未来があるのではないかと思っております。弊社は長年の障がい者雇用で培ってきた歴史があるので私たちの地域の人達は理解を示して下さり生き辛さを抱えている人達が地域で安心してくらせるようになりました。皆さま方にも小さなことから出来る範囲で無理しないで頑張っていって頂ければ幸いです。
〈感想〉
廣田:訪問看護事業や相談支援事業、グループホーム事業など、さまざまな形で支援を実施されており、支援を必要とする方々に適切なサポートを提供されていることが本当に素晴らしいとの思いを抱きました。特に自立支援についてお尋ねした際にお答えいただいた、本人の意思を尊重したうえで、本人の力を引き出し、さらに引き伸ばしていくというお考えは、「南大阪自立支援センター」という名前が示す理念そのものだと感じ、大変感銘を受けました。