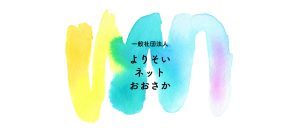《街のよりそいさん数珠繋ぎ》(インタビュー13回目)
インタビュアー:よりそいメンバー
記事作成:よりそいメンバー
〈インタビュー日〉2025年7月18日(金)
〈今回のよりそいさん〉交野女子学院のみなさん
前田さん(庶務課長)
相宅さん(庶務係長)
久保田さん(庶務係)※3月までは教育支援部門だったため、そちらの目線でインタビューにお答えいただきました。
山本さん(福祉専門官)
山田さん (心理技官)※山田さんは2つ目の質問から参加していただきました。
Q.普段はどのような業務をされていらっしゃるのでしょうか。
A.
前田さん:庶務課長の前田です。庶務課の監督者ということで庶務課業務の監督業務、そして人事関係の業務(採用、異動、辞職に関すること)などを行っています。
相宅さん:庶務係長の相宅です。庶務係長になったのは今月からでして、職員の勤務時間の管理や人事を担当しています。先月まで契約や予算管理などの係長をしていたので、庶務係長にはなったばかりです。
久保田さん:3月まで教育支援部門の集団寮で寮勤務をしていた久保田と申します。寮勤務をしていた時は、少年に対して生活指導や職業指導、生活の中での相談相手をしていました。4月からは庶務係なので少年の生活指導には全く関わらず、文書の受付や接遇などをしています。
山本さん:福祉専門官の山本と申します。私は少年の社会復帰支援の中でも特に福祉的支援を担当させていただいています。
Q.お仕事をしていて感じるやりがいについて教えてください。
A.
前田さん:監督者という立場なので、皆さんが何の問題もなく毎日を過ごして仕事が終わったというのが私としては一番責任を全うしたかなと思っています。私自身というよりかは周りの職員が色々なことを達成できたらそれが喜びですね。
相宅さん:予算の管理をしたり契約をしたりするので、椅子を一つ買うにも会計法に基づいて適正な進行をして調達しています。ただ、椅子を買うといっても色々な椅子があると思います。どこかが壊れたら新しいものを買うけれどそれは国民の税金で買っているものなので、壊れたからといって簡単に買うことはせずに直せるものはこちらの手で直しています。この間はエアコンを直して、業者を呼んで何万かかるっていうのを浮かせました。ものを買うにしてもしっかりと調べて知識をいれて良いものを選定しよう、安く買おうということは心がけて勤務しています。全く法務教官っぽくはないけれど公務員としてのやりがいです。
久保田さん:教育支援部門のときのやりがいについてお話しさせていただきます。少年と毎日対峙して色々な話をする中で、やはり一日一日どこかは成長しているんですよね。でも一歩戻って、また一歩進んでという繰り返しです。仮退院の時には「ありがとう」と一言もらえることもあるので、そういうのがすごくやりがいにつながっているかなと思います。反抗されたりボロカス言われたりもしますが、色々なぶつかりがあっての「ありがとう」の一言なので、すごく大きいなと思います。
山本さん:出院後に支援者とつながったり支援を利用したりしてちゃんと社会復帰できているよという話を聞いたときに良かったなと思い、それがやりがいにつながっています。
山田さん:心理技官の山田と申します。去年の春に初めて少年院の配置の心理技官になり、それまでは少年鑑別所や刑事施設の方で勤務していました。少年鑑別所等では心理のアセスメントが中心になるのですが、少年院の方はどちらかというとトリートメントや教育が中心になります。鑑別所や刑事施設は本当に短期間の調査という色合いが強いのですが、こちらの方は半年から11カ月延びる少年がいて、そういう人と関われる所が全然違うし、変化というのがその分少年院では多いなと思っています。進級をどんどんして行くうちに少年自身が変化するのを見ることができるのがすごくやりがいかなと思っています。
Q.お仕事をされる中で、ご自身の中で変化したことなどはございますか。
A.
前田さん:変化というと「矯正」自体が今変わりつつありますね。自分自身が変わったというよりは、周囲が変わってきているのかなと感じています。期待していることは、更に
良い矯正になればいいなと思っています。私もあと3年ほどで期間満了になるので、それまでに何か良いことがないかなと期待しています。
相宅さん:1番は色々なことを調べるようになったことですね。仕事をする前は他人事なことが多く、「どうでもいいし」みたいな性格だったのですが、仕事をしていく中で責任を持って仕事をしていかないといけないということで、色々なことを調べて考えていくことが増えましたね。
久保田さん:私はもともと被害者支援をしたくて警察官を目指していました。法務教官は加害者支援というイメージがあったので、やりたいこととは真逆でした。それこそ採用された1年目の最初の頃はすごく抵抗がありました。面接で非行少年と1対1で話す時など、少年たちが普通にしゃべったり、笑ったり、逆に怒ることもあったりするのですが、こんなことをしていて被害者の人はどう思っているのかなと、そんなことが頭にありました。しかし、その支援をしている先生のお仕事の内容や、少年院で取り組んでいる行事の内容を知っていく中で、少年たちを更生へ導くことがこれからを増やさないことに繋がっていくのだというように考え方が大きく変わりました。これが教育支援部門にいたときの話ですね。庶務課に来て変わったところが、職員のことや諸手当などの管理をするのですが、また違う責任の重さがありますね。さらに責任感が強くなりました。
山本さん:前は医療機関に勤めていて、今までは「仕事ってなんとかなる」と、何も考えず、ただ行って働いて帰ってという感じでした。しかし、こちらに来てからは少年院法や法律、内務規定などが決められていて、仕事に対して少しきっちりするようになったのかなと思います。 しんどい時もあるけれど、もっとしっかりしないといけないなというように成長したのかなと思っています。
山田さん:仕事に関しては、就職する前は「仕事=働かなきゃいけない」というイメージでしたが、ずっと働いてみると働くことが日常生活になっています。もちろん朝が来た時に「仕事しんどい、休みたい」と思うこともあるけれど、働くのが日常になってしまったなという感じが時間や計画ともに変わってきていることかなと思います。また、変わらず学ぶこと自体がすごく幅広くて多いなというのを実感しています。 でも、学ぶことだけではなくて、仕事が忙しいけれど楽しいことも多いなとは思っています。遊ぶのも大事で、色々なものを見たり食べたり経験することも仕事の中で活かせるのかなということをすごく感じています。
Q.入院してくる少年たちはどんな背景や事情を抱えていることが多いですか?
A.
山田さん:男子少年院と女子少年院では背景が全く違う部分があって、女子少年の場合は「家庭を見なさい」と言われてきました。そこに注目して見ていたのですが、実際に家庭環境が複雑であったり、親子関係がうまくいっていなかったりと、家族関係の複雑さをすごく実感しています。少年院から出るときには帰る先が必要なのですが、その調整に時間がかかる少年もいました。一般の人だと帰る家があって、住むところも食べるものも困らないというのが普通だと思いますが、少年の場合はなかなか十分に確保できていない人が多いので、やはり家族関係というのは非行の背景にあるかなと思います。その分、異性関係が大事になってきていて、異性関係から薬物につながることもあるので、非行にもつながってくるのかなと思います。
Q.女子の非行は男子の非行と比べて実際に接していてどのような特徴の違いがありますか?違いがあった場合、女子ならではの難しさや支援上の工夫はありますか?
A.
山田さん:やはり男子と女子で非行は全然違ってきます。刑法犯で見ると、男性が9割としたら女性はその10分の1ぐらいで、女性の方が圧倒的に少ないです。性別による違いは絶対にあって、その分犯罪の出方にも違いがあります。ただ、男子の場合は基本的に交通非行が多く、無免許運転や集団暴走、今では仲間同士で少し走るか暴走行為をするというパターンが増えています。特殊詐欺や受け子などは男子の方が多いです。ちらほらと女子の少年もあるのですが、数としては男子の方が多いです。薬物非行で見ると、女子の方が割合が高く、特に大麻よりも覚醒剤で入ってくることが女子では多いです。男子の場合は覚醒剤が少なく、大麻が中心になっています。女子の場合は異性関係から薬物非行にはしることが多いので、大人と一緒に覚醒剤をする、勧められてするというパターンが多く、どうしても覚醒剤などの事案が多くなってしまうという違いがあります。
Q.交野女子学院では職業訓練で介護系の職業が人気だとHPで拝見したのですが、さまざまな背景を抱える子が介護分野を選ぶ際は、どのようなことに配慮して教えていますか?
A.
久保田さん:介護福祉科は少年院の職員が指導しているというよりかは、福祉施設で働いている、その免許を持っている方に授業をしに来ていただいています。介護福祉科は希望が多いので、「この子は介護福祉科に推薦しよう」と、職員がたくさんある希望の中から生活態度などを見て介護福祉科を最後まで反則行為をせずやり遂げられるという子を推薦して授業を受けてもらうという形になっています。介護の授業に選ばれた時点でその子たちにはそういう話はされているので、「こういう理由で選ばれているから、責任をもって最後までやりなさいよ」と伝えています。なので、ちゃんとした態度で講師の方の話を聞いている子が多いですね。
山本さん:初任者研修の資格が講義を受けて試験を受けたら取れるので、資格を取って住み込み就労ができるように私たちが環境を整えています。
久保田さん:でも、ルール違反する子もいるので、そういう子は途中で授業を受けられなくなります。
山田さん:こちらは授業を受ける子を選ぶ側になるのですが、希望を聞いてから選んでいます。受講しないといけないコマ数が決まっているので、反則行為をしてしまうと取れなくなってしまうという事情があります。
久保田さん:受講する前には、本人たちにはあらかじめ「反則行為をすると受けられなくなる」と伝えています。
Q.将来、少年非行や更生支援などに関わりたいと考えている学生にアドバイスはありますか?
A.
前田さん:今回のインタビューも採用広報活動の1つですが、皆さんを含め、多くの方が法務教官を目指してみようと思っていただければ有難いと思います。
山田さん:心理テストの勉強は学部生の時はほぼできないし、大学院に通っていた時は院生同士で取り合うくらいしか経験がなかったけれど、矯正に入ると研修自体もしっかりしているし、全くできなくても入れる場所がありますし、やる気や興味があるという人はどんどん来ていただけたら。もし本当に興味があってどんな所なのかもっと詳しく知りたい方にインターンシップのようなものも春と夏に少年院や少年鑑別所でやっているので、体験してみたらより分かるのかなと思います。
相宅さん:何でも経験してくれたらいいかなと思います。少年たちと一緒に寮に入って一緒に生活をする中で「困ったんですけどどうしたらいいですか先生」と言われた時に知っていないと答えられないので、色々なことを経験して来てくれたらいいかなと思います。物とかの方が詳しくなってしまったので、「壊れちゃったのでどうしたらいいでしょう」に対して「こうやったらいいんだよ」と話したり、あらゆることを知ったりしてくれたらいいかなと思います。
Q.女子ならではの対応の難しさや困ること、工夫していることはありますか?
A.
相宅さん:職域拡大が数年前に始まり、男性の教官を女子施設に、女性の教官を男子施設に配置するということが始まっているところです。女の子に接するとき、一般的に考えるとセクハラと言われないか気にしています。
山田さん:カメラや職員が充分に巡回できる部屋でないと面接ができないという決まりが全国的にあるので、全体的にすごく気を遣っているなというのがありますが、女子は特に距離感を大事にしているなというのがあります。男子少年よりも話し込みが多く、関係性も大事なのでそのあたりは難しいなと思っています。男子の方がさっぱりしていて、一緒に運動や作業をするところが大きいのですが、女子はお話も面接も大好きで、自分自身だけではなく寮の先生もすごくいっぱい話しているなという印象を持っています。
<感想>
インタビューだけでなく施設見学までさせていただき、日々の取り組みや男女の違いによる対応の違い、皆様が普段意識していらっしゃることなど、実際に見聞きしながら様々なことをお伺いすることができました。そこから少年たちを支えることの難しさと大切さ・重要さを改めて感じました。
今回の経験を通して、非行の背景にある複雑な事情や、そこから立ち直ろうとするシステムとそれを支える方々のお考えに触れ、私たち学生にも大きな気づきがありました。
お忙しい中、職種も様々な方々にご対応いただきましたこと、お礼申し上げます。